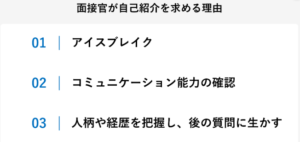福岡リート誕生秘話

「坂の上の雲」風に
「福岡発の上場不動産投資信託2006」(ノンフィクションドラマ)冒頭ナレーション
まことに小さな地方の開発会社が、開化期を迎えようとしている。
小さなといえば、2004年の福岡地所ほど危機的な小さな不動産開発会社はなかったであろう。
持つべき資産としてはキャナルシティ博多くらいしかなく、人材といえば50年間、ハードネゴシエーションと中洲で鳴らした、営業部隊であった旧士族やラガーマンしかいなかった。
福岡リート投資法人設立と上場によって、福岡地所の人々ははじめて近代的な「運用会社」というものをもった。誰もが「プロパティ・マネージャー」になった。
不慣れながら「PM」になった福岡地所人たちは、日本の地方市場初の上場不動産投資信託の体験者としてその新鮮さに昂揚した。
この痛々しいばかりの昂揚がわからなければ、この段階の歴史はわからない。
それまでの、会社のどういう階層のどういう部門の人間でも、ある一定の資格を取るために必要な記憶力と根気さえあれば、AMにもPMにも、投資運用委員にも鑑定士にも会計士にも弁護士にもなりえた。
この時代の明るさは、こういう楽天主義(オプティシズム)から来ている。
今から思えば実に滑稽なことに、ラースタとシネコンの他に主要テナントのないこの不動産会社の連中が、名だるる東京の不動産会社と同じ上場不動産投資信託を持とうとした。金融庁認可会社の運用会社も同様である。
成功の確率が成り立つはずは無い。
が、ともかくも運用会社と上場不動産投資信託を創り上げようというのは、もともと福岡地所の企業再生の大目的であったし、創業者に連なるメインバンクであった福岡シティ銀行に育てられた、このプロジェクトに踏み出した新生福岡地所の者達の「少年のような希望」であった。
この物語は、その小さな不動産開発会社が、あらゆる艱難を乗り越え、ヨーロッパやアメリカにおける最も古い、強大な債権者らと対決し、そしてどのように振る舞ったかという物語である。
主人公は、あるいはこの時代の小さな福岡地所それ自体ということになるかもしれない。
ともかくも、我々は五人の人物の跡を追わねばならない。
博多と天神の結節点、1996年開業のキャナルシティ博多に、男たちが集った。世に言う、七人の侍である。
この古い商人の町に生まれ、米国留学帰りで外資系コンサルティング会社に就職が決まっていたのを蹴った一番目の男は、福岡シティ銀行の経営危機が迫るにあたって、上場は不可能に近いといわれた福岡リート投資法人の上場構想を立て、それを実施できる人間を集め、それを実行させた。
その大学時代の友人の弁護士の男は、自身の弁護士事務所の屋号を捧げて、運用会社のコンプライアンス精神を育成し、日本最強の弁護士集団である、MM法律事務所やNA法律事務所と渡り合うという奇蹟を遂げた。
もうひとりは、神宮球場で鳴らしたその左腕から繰り出す強肩で鳴らした有能な野球選手の経歴を引っ提げ、不動産投資といえば不動産担保融資くらいしか従事したことのなかった身から、流動化、証券化といった日本の古い取引慣行に新風を入れてその中興の祖になった。
さらにもう一人は、桜島一周マラソン5位以内、フルマラソン3時間10分の実績と体力、そしてよくわからない都市工学という大学院卒と見まがう6年の修養期間を経て最初に福岡地所に新卒で入社し、修羅の国北九州のリバーウォークで研鑽を積んだ。彼の繰り出すエンジニアリング・レポート特記事項潰しに、どれだけの金融機関や目論見書作成者が救われたかわからない。
最後に、筆者である。上の四名とは別の大学を卒業し、同窓でも同僚でもなく、前職時代の社宅が隣同士でもない、ただ北九州市八幡出身、七色の煙を吸って育ったというだけで、親がかの工藤會さんと渡り合った小倉南署の刑事であることから、鉄砲玉として騙されて勧誘されたものである。
彼らは、福岡地所の危機的状況にあたり、昭和生まれという時代人の体質で、前をのみ見つめながら歩く。
登っていく坂の上の青い天に、もし一朶(いちだ)の白い雲と上場益、そして福岡の面白い街づくりと人々の笑顔が輝いているとすれば、それのみを見つめて、坂を登ってゆくであろう。
~つづく~